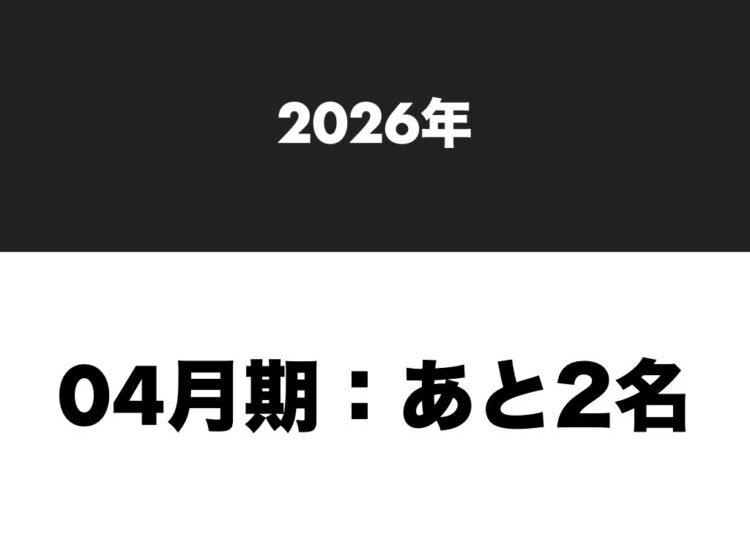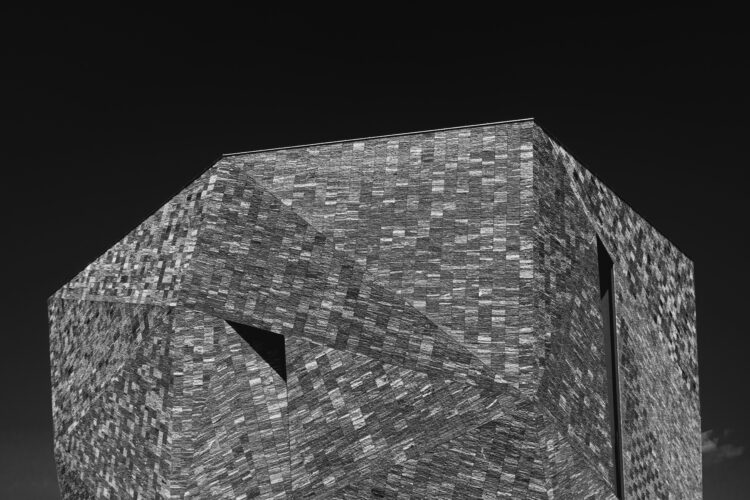エンジニアのための「プロデューサーと建設的に戦う技術」

「仕様が固まっていないので動けません」
「その変更には技術的な根拠がありません」
開発や制作の現場において、クリエイターが口にするこれらの言葉。 これらは決して間違いではない。
品質を担保し、納期を守る責任があるからこそ、エンジニアやデザイナーは曖昧さを排除しようとする。それはプロとしての正常な防衛本能だ。
しかし、もしあなたが「言われた通りに作る」だけではなく、ビジネスを動かすコアメンバーとして活躍したいと願うなら、この「正論」の使い方を少しだけ変える必要がある。
論理(ロジック)は、相手を突き放すための「壁」ではなく、不条理なビジネス課題を解決するための「共通言語」であるべきだ。
今回は、プロデューサーやビジネスサイドと、技術者がいかにして「対等かつ建設的な議論」を行い、プロジェクトを成功に導く
か。そのための視座について考えたい。
「ただ作るだけ」の人間は、AIに淘汰される
まず、残酷な現実を直視することから始めよう。
かつて、コードが書けること、整ったデザインが作れることは、それだけで希少価値だった。だが、生成AIの進化は、その「技能」の価値を暴落させた。
明確な仕様書さえあれば、AIは人間よりも速く、正確にコードを書き上げる。的確なプロンプトさえあれば、平均点以上のデザインを一瞬で生成する。
つまり、「言われた通りに作る」という領域において、人間はもはやAIの下位互換になりつつある、いや、なった。
今後淘汰されるのは、プロデューサーの曖昧な指示を嫌い、ディスプレイの中だけで完結しようとする「作業者」だ。彼らが誇る技術力は、AIによって容易に代替される。
逆に生き残るのは誰か。それは、AIには理解できない「人間の感情」や「ビジネスの政治」、「市場の空気」といった不合理な変数を計算に入れ、関係者と調整しながら最適解を導き出せる人材だけである。
プロデューサーが見ている「不条理」な景色を想像する
なぜ、プロデューサーの指示は時に曖昧で、朝令暮改なのか。 それは彼らが、最も予測不可能で不条理な「市場(ユーザー)」と最前線で対峙しているからだ。
「昨日はAだと言っていたユーザーが、今日はBを欲しがっている」 「競合が突然、革新的な機能を出してきた」
こうしたカオスな状況下で、彼らは必死に正解を探している。その揺らぎが、そのまま現場への「変更指示」として伝播してくる。
これを「ブレている」と批判するのは簡単だ。しかし、真のプロフェッショナルは、相手が見ている景色を想像しようとする。
「なぜ仕様が変わったのか? そこには市場のどういう変化があったのか?」
その背景に思いを馳せたとき、あなたのロジックは批判のためではなく、解決のために機能し始める。
「仕様変更は困ります」の前に、「その市場変化に対応するなら、仕様変更よりも、まずは既存機能の改修でテストしませんか?」という、建設的な提案をしてみる。
“数字””顧客との約束”を背負うプロデューサーには、何が見えているのか?
「御用聞き」ではなく「参謀」としてのクリエイター
ビジネスサイドの要望を全て鵜呑みにするイエスマンになる必要は全くない。
むしろ、技術のプロとして「それはやるべきではない」と提言することこそが重要だ。ただし、その際は「技術的に無理」で終わらせず、「ビジネスのゴールを達成するための代替案」をセットにするのが鉄則。
■悪い例:
「その機能は無理です」
■良い例:
「その機能をフルスペックで作ると2ヶ月かかりますが、検証が目的なら、既存ツールを組み合わせて1週間でリリースする『B案』が可能です。こちらで市場反応を見れるか?」
これが「視座を合わせる」ということだ。
プロデューサーが求めているのは「機能の実装」そのものではなく、その先にある「課題解決」。
技術者は、プロデューサーが持っていない「解決策(How)」の引き出しを無数に持っている。その専門性を武器に、相手と同じゴールを見据えて議論する。その姿勢があれば、あなたは単なる作業者から、かけがえのない「参謀」へと進化する。
カオスを楽しめる技術者が、最強のチームを作る
アクトハウスが「Art & Science」や「Business」を包括的に教える理由は、まさにこの「対話力」を育むためにある。
コードが書けて、デザインも分かる。さらにビジネスの力学も理解している。 そんな人材であれば、プロデューサーの「感覚的な要望」や「無茶な相談」の裏にある本質的な意図を汲み取り、技術的な最適解へと翻訳することができる。
「ここは論理的には非効率ですが、ブランド価値を高めるためには絶対に必要な『遊び』です」 「この機能は削っても、UX(ユーザー体験)には影響しません」
このように、技術とビジネスの境界線を越えて踏み込んだ発言ができるクリエイターがいるチームは強い。そこには、職種の壁を超えた「共犯関係」が生まれるからだ。
ロジックを「対話」のテーブルに乗せよう
「仕様が決まらない」と嘆く前に、技術的な観点から仕様を提案してみよう。 「指示が曖昧だ」と突き放す前に、何がベストなのかを一緒に言語化してみよう。
論理は、相手を論破するためにあるのではない。 混沌としたビジネスの海で、チーム全員が迷わないための羅針盤を作るためにある。
不条理な市場に向き合うプロデューサーと、論理を操るクリエイター。 この両者が互いにリスペクトを持ち、建設的に常時ぶつかり合う場所でこそ、人の心を動かす本物のサービスは生まれる。
半年後、あなたは自分のスキルを「守る」ために使うのか。
それとも、チームを「前進させる」ために使うのか。
アクトハウスは、後者を目指すあなたを待っている。
著者:清宮 雄(アクトハウス代表) 起業家・ブランドアーキテクト。2014年にセブ島でIT留学の草分けアクトハウスを設立。「ビジネス×テック」をテーマに、時代に左右されない強靭な個の育成=「+180 ビジネステック留学」の戦略・運営を主導。